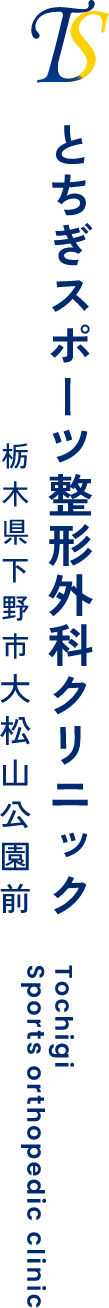肩関節の整形外科
「肩」の特徴
肩は動く範囲を広くするために骨による支えが乏しく、筋肉により安定性をえている関節になります。
肩はピンに乗っているゴルフボールによく例えられます(不安定なイメージになります)。
そのため肩は、ヒトの身体の関節で最も脱臼しやすい関節と言われています。
肩の安定にとって大切なものが筋肉になります。
その筋肉は「腱板(けんばん)」と呼ばれ、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋の4つの筋で構成されます。
肩の動きや安定を良くするためにはこの腱板(肩のインナーマッスル)がしっかりと動く必要があります。
①肩の痛みで頻度の多いもの
「肩こり」、「五十肩」、「腱板断裂」
「肩こり」とは?
肩こりは病名ではなく症状になります。
病名では「頚肩腕症候群(けいけんわんしょうこうぐん)」と呼ばれます。
肩こりは基本的には後頚部、背部、肩周囲の筋肉の過度な緊張による疼痛や張りとなります。
ヒトの頭の重さは、体重の約8%と言われていますが(60kgの人で約5kg)、スマホなどを見る際に首を前側に倒すと背中には頭の重さの約4倍の負荷がかかるとされています。
肩こりは、筋肉の緊張によるものなので筋肉の緊張をときほぐすような治療により効果がみられます。
代表的な治療としましては、ストレッチ、マッサージ、電気治療、超音波治療、温熱治療、鍼灸などがあります。
一方でこのような治療を行って一時的に筋緊張の改善がえられても、仕事での負担や生活習慣、姿勢不良、体幹下肢の筋力の弱さなど、慢性的に負荷がかかると肩こりもなかなか改善がみられません。
肩こりの治療では、肩のみの治療ではなく、「肩に負担のかかりにくい動きやすい身体をつくる」ことが大切になります。
「五十肩」とは?
五十肩は、病名では「肩関節周囲炎」、「癒着性肩関節包炎」と言われます。
是非、ご理解して頂きたいことは、「五十肩」と「肩こり」は身体の中で起こっていることが大きく異なり、そのため治療法も大きく違うということになります。
「五十肩」では肩の中で炎症が起こっているため肩を動かす事で強い痛みが生じます。
症状が悪化しますと夜間痛と言われ、痛みにより夜眠れない方もいらっしゃいます。
その治療は、炎症を鎮めることが目的になりますので、安静、鎮痛薬内服、炎症部位への注射などが一般的となります。
当院では「五十肩の専門外来」におきまして、更に一歩進んだ治療として、「外来で行う肩関節授動術」を行っております。
「腱板断裂」とは?
腱板とは、肩を動かす時に使われる筋肉の総称で、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋の4つの筋で構成されます。
肩のインナーマッスルと呼ばれ、肩関節を安定させながら、腕を様々な方向へ動かす力源となります。
腱板は年を重ねると自然に傷んでくることもありますし、転倒などの外傷により傷めてしまうこともあります。
その代表的な症状としまして、 「肩に力が入りにくい(腕を持ち上げにくい)」、「肩を動かすと引っかかりや痛みが出る」などがあります。
症状と合わせて超音波(エコー)やMRIで診断を行います。
治療は、肩を傷めにくい動かし方をご理解してもらい、痛みに対しては鎮痛薬や注射、またリハビリテーションによる肩機能の改善も重要となって来ます。
そのような治療で症状の改善がなければ手術を行うこともあります。
手術はカメラを用いて、小さい傷で行うことが出来ます(損傷が大きい際は手術の方法が異なります)。
その他の肩の疾患に関して
「石灰沈着性腱板炎」とは?
「肩のレントゲンで石灰が写っています」と言われたことがある方がいるかもしれません。
石灰とはカルシウムが筋肉内などに沈着することで起こり、強い痛みを起こすことがあります。
中には激痛で全く肩を動かせない状況で病院受診する方もいます。
石灰沈着性腱板炎には、注射が効果的です。
五十肩と同様に40~50代の女性によくみられますが、肩の激痛がみられる場合は早めに病院やクリニックの受診をお勧めします。
「変形性肩関節症」とは?
変形性肩関節症は、ヒトの関節を構成する軟骨がすり減り、骨が変形を来す状態になります。
レントゲンを撮ることで診断が出来ます。
一般的には、膝関節、股関節など体重の負担がかかる関節に多くみられますが、肩関節にも生じることがあります。
症状としては、肩を動かす時の痛みやごりごりした感じ、動きの制限などになります。
積極的な運動やリハビリで肩の動きを出すと悪化する可能性があるため注意が必要です。
また変性した軟骨の再生は、現在の医学でも十分ではなく、関節を正常に戻すことはまだ難しい状態です。
現実的には、変形性した肩には負荷をかけないような生活を心がけ、痛み止めの内服や注射、無理をしないリハビリで経過をみることが多くなります。
どうしても痛みが取れない時は、手術を行うこともあります(人工肩関節置換術)。
「反復性肩関節脱臼」とは?
肩は最も脱臼を起こしやすい関節になります。
スポーツや転倒などの外傷がきっかけとなり脱臼を繰り返す状態を反復性肩関節脱臼と呼びます。
様々なスポーツで起こることがありますが、特に10代で生じた肩の脱臼はその多くが反復性脱臼となるため注意が必要となります。
また、脱臼の回数が増えるほど肩関節が壊れて行き、脱臼しやすくなります。
治療はリハビリにより肩の安定性も高めることも大切ですが、スポーツや仕事に支障が出るようであれば手術を行うことが多くなります。
手術はカメラを用いた関節鏡による手術や肩の前方を切開し、烏口突起と呼ばれる骨を肩前方に移行する手術などがあります(肩の状態により手術方法が異なります)。
「ルースショルダー」とは?
動揺肩(どうようかた)とも呼ばれます。特に外傷などにより肩脱臼の経験がなくても肩が緩い方がいます。
関節の柔らかさには、生まれつきの個人差もあり、もともと関節が柔らかい方が肩の痛みや緩さ、不安感(肩が外れそう)などを感じることがあります。
治療としてはリハビリにより肩を安定させるトレーニングなどを行います。
「肩インピンジメント症候群」とは?
インピンジメントとは「衝突」、「挟み込み」を意味します。肩を動かした際に骨と骨がインピンジメントを起こして痛みを生じさせます。
肩の筋肉の緊張や疲労、肩甲骨の動きの不良などで肩がスムーズに動かないことで起こります。
治療はリハビリにより肩の機能の改善になります。
腱板断裂や石灰沈着性腱板炎、五十肩でも似たような症状が起こるため鑑別が必要になります。
「リウマチ肩」とは?
関節リウマチという病気を聞いたことがあるかと思います。
関節リウマチとは、自身の免疫反応により自身の関節を壊してしまう疾患になります。
症状が進行しますと骨や軟骨が変形を起こします。手足の関節に起こりやすいですが、肩関節にも起こることがあります。
診断は、症状、画像検査、血液検査などで複合的に判断します。
基本的にはクスリによる治療が中心となりますが、関節の変形の痛みが強い場合は手術を行うこともあります。
※関節リウマチはクスリによる治療が中心であり、クスリの種類も多様であるため当院ではリウマチ内科へご紹介させて頂くこともあります。
「上腕二頭筋長頭腱炎」とは?
肩の前方には二の腕の「力こぶ」につながっている腱が走っています。
この腱が炎症を起こす状態で、肩の前側を押すと痛みがみられます。
肩を捻る、ペットボトルや硬い瓶のフタを開ける、肘を強く曲げる動作などでこの腱に負担がかかり痛みが生じることがあります。
超音波検査(エコー検査)で腱の腫れや腱周囲の水の溜まりを観察することが出来ます。
治療は注射やリハビリを行うことが多くなります。
「胸郭出口症候群」とは?
胸郭出口症候群は、鎖骨と第一肋骨の間を走る神経、血管が圧迫されることで生じる疾患になります。
症状は多彩で、肩の運動時痛、肩から腕のしびれ感、だるさ、違和感、握力の低下、手の浮腫みなど幅広い症状がみられます。
手を高く挙げたり、首や肩に負担のかかる職業や姿勢の不良、野球などスポーツで起こることがあります。
ドライヤーをかける時や電車やバスのつり革につかまっている時などに症状が出やすくなります。
治療は、生活指導、内服治療、リハビリなどになります。
症状の改善が得られない時は、第一肋骨の一部を切除して、神経と血管の通り道を広げる手術を行うこともあります。